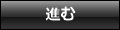今後の備え(二つの成年後見制度について)
口座が凍結された、入所契約ができない、自宅の売却ができない…
認知症などになり、判断能力が衰えてしまうと、金銭管理や契約のような法律行為ができなくなってしまう可能性があります。
そこでご自身の判断能力の低下への備えとして、今のお元気なうちにご家族や親しい方、また専門家と「任意後見契約」を結んでおくことはとても有効な手段であると思われます。
しかしながら、手続きが難しそうであったり、公正証書で作成しなければならないなど、ちょっと敷居が高いイメージがあります。
また、毎月後見人に支払う報酬や、家庭裁判所が選任する後見監督人への報酬など、費用がどれくらいかかるものなのか、なかなか見当がつかないのではないでしょうか。
任意後見契約は、他の契約形態と組み合わせることで、判断能力が衰えてしまう前や、判断能力が衰えてから亡くなるまで隙間なく支援を受けることができたり、ご自身が亡くなった後の事務を委任したりすることも可能です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

二つの成年後見制度の利点や使いにくい点を理解していただいたうえで、制度の利用をご検討いただければ幸いです。