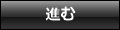人が亡くなった後の手続き その③
故人の生活に関する手続き
・医療費、入院費等の清算手続き
・医療保険金の請求(3年以内)
・老人ホームなどの施設利用料等の支払い
・公共サービス(電気・ガス・水道・固定電話・携帯電話・NHKなど)の名義変更・解約・清算に関する手続き
・生命保険金の請求(3年以内)
・運転免許証、パスポートの返納など
・生活用品、家財道具などの遺品の整理・処分
・インターネットのプロバイダー契約、ホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、各種解約や退会処理に関する手続きなど
公共料金を亡くなった方の口座から引き落としている場合、金融機関が死亡したことを把握しますと、口座が凍結され取引ができなくなりますので、早めにご家族などの口座に引落し先を変更しておく必要があります。
パソコンやスマートフォンで管理しているものの扱いには注意が必要です。
電子媒体の管理はご本人の中で完結しているものが多く、情報を残さずに亡くなると、対応が難しくなってしまいますので、生前にこれらのIDやパスワード、解除方法などをわかりやすくまとめておくのがよろしいかと思います。
権利や義務に関する手続き
・相続放棄・限定承認(3か月以内)【家庭裁判所】
・準確定申告(4か月以内)【税務署】
・相続税申告(10か月以内)【税務署】
・預貯金、不動産、自動車等の相続手続き(遺産分割協議)
相続放棄を「する」、「しない」については、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続財産の目録を、生前にある程度ご自身で作成しておくと、相続人の方が判断しやすいかもしれません。
相続財産目録は、相続税の申告が必要かどうかの判断材料にもなりますし、相続人が遺産分割協議を行う場合にも、あればとても参考になります。

このように、人が亡くなったあとの手続きを理解しておくと、エンディングノートでどのようなことを情報として残しておけばよいかのヒントになるかもしれません。