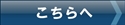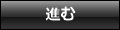遺産分割協議 その③
相続財産目録の作成
相続人の調査と並行して、相続の対象となる財産を整理し、「相続財産目録」を作成していきます。
○相続の対象となる財産の例として

・不動産〔土地や家屋(抵当権や借地権なども含む)〕
・動産〔自動車、貴金属、骨董品など〕
・有価証券〔株式、国債、社債、ゴルフ会員権〕
○財産にはマイナスの財産もあります
・負債〔借金、ローンなど〕
・公租公課〔未納、滞納の税金など〕
・保証債務〔保証人、連帯保証人の債務など〕
・損害賠償債務〔不法行為、債務不履行など〕
・買掛金〔未払いの債務など〕
○相続財産とみなされないもの【参考】
・祭祀財産〔墓地、仏壇、位牌、遺骨など〕
・香典、葬儀費用、埋葬費用
・生命保険金(故人以外が受取人)
・死亡退職金
・故人の一身専属的な権利〔地位、特許など〕
このように相続財産を整理し、金融資産の残高や不動産の相続税評価額を積算することで、相続税がかかるかどうかのおおまかな目安になります。(相続税の課税価格には生命保険金や死亡退職金などが加算されます)
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
これに近い額になった場合、詳細は税理士に相談することをお勧めします。(市町村役場の無料税務相談などをご利用されるのがいいかもしれません)
また、配偶者控除や小規模宅地の特例といった各種控除を使う場合、基礎控除額を下回っていても税務署への申告が必要になります。
遺産分割協議書の作成
「相続人の確定」(第1段階)、「相続財産目録の作成」(第2段階)が完了して、ようやく相続人間で「遺産分割協議」の話し合いを行うことができます。
相続財産をどのように分けたいか、相続人の代表者の方から聞き取りを行い、遺産分割協議書の素案を作成します。
たたき台として作成した素案を使って、相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、必要に応じて修正しながら「遺産分割協議書」を完成させていきます。
完成した遺産分割協議書に相続人全員の「署名」「実印での押印」を行い、「印鑑登録証明書」を添付して完成となります。
※日頃から実印と印鑑登録カードのありかを確認しておきましょう
協議で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「調停」や「審判」へと移行していくことになります。
自分でやってみたところうまくいかなかったので、「相続人の確定のために戸籍を揃えて相続関係説明図を作ってほしい」、「法定相続情報一覧図を作成し法務局で証明を取れるようにしてほしい」、「相続財産目録だけ作ってほしい」など、個々の書類の作成だけでも承ります。
当事務所までお気軽にご相談ください。