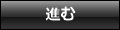死後の備えと相続(遺産分割協議書の作成に向けて)
戸籍の収集、相続財産の特定、遺産分割協議などが大変…
人が亡くなった後、その方が法的に有効な遺言書を残されていない場合、多くの相続手続きにおいて「遺産分割協議書」を求められます。そのため、ご家族などの相続人が全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議はなかなか大変な手続きですので、残されたご家族にできるだけ負担にならないよう、法的に有効な「遺言書」を残しておくのはいかがでしょうか?
遺言なんて「縁起でもない」と敬遠される方もいらっしゃるかと思いますが、遺言書は遺書ではありません。
遺言書であなたの意志を残しておくことは、能動的なことで、残されたご家族のための作業になります。
まず最初は自分でできる「自筆証書遺言書」を作成してみるのはいかがでしょうか。ただし、方式上の違反などがありますと、有効な遺言書とみなされない可能性がありますのでご注意ください。
自筆証書遺言書は 「法務局の保管制度」が創設されるなど、相続法の改正によって使い勝手が良くなりました。

ご自身の死後、残されたご家族の負担をさらに減らしたいとお考えの方は、社会的な信用のある「公正証書遺言書」の作成をご検討されてみるのもよろしいかと思います。